医療費が高額になるとき(高額療養費や限度額適用認定証など)

医療費の自己負担限度額の区分は、 年齢や所得に応じて下記のとおりに定められています。
医療機関で支払う金額がご自身の自己負担限度額を超えている場合、上のフローチャートを参考に手続きしてください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(負担区分「オ 住民税非課税世帯」又は「低所得者2」)の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、申請手続きが必要です。
注意
- 各種手続きには、本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。
- 別世帯の人が手続きする場合、別途委任状が必要です。
- 手続きの際、マイナンバーがわかるものが必要な場合があります。
70歳未満の人の場合
原則として、同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払う金額の自己負担限度額
| 所得区分(※1) | 自己負担限度額(平成27年1月1日から) |
| ア 所得 901万円超の世帯 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [4回目以降 140,100円](※2) |
| イ 所得600万円超901万円以下の世帯 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [4回目以降 93,000円](※2) |
| ウ 所得210万円超600万円以下の世帯 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [4回目以降 44,400円](※2) |
| エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)の世帯 |
57,600円 [4回目以降 44,400円](※2) |
| オ 住民税非課税世帯 |
35,400円 [4回目以降 24,600円](※2) |
※1 所得申告のない場合は、上位所得者(ア)とみなされます。
※2 過去12か月間に、1つの世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額になります。
70歳以上74歳以下の人の場合
| 所得区分 |
自己負担限度額(平成30年8月から) |
|
| 外来のみ | 外来+入院 | |
|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上の世帯) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [4回目以降 140,100円](※5) |
|
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上、690万円未満の世帯) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [4回目以降 93,000円](※5) |
|
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上、380万円未満の世帯) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [4回目以降 44,400円](※5) |
|
| 一般 |
18,000円
|
57,600円 [4回目以降は44,400円](※5) |
| 低所得者2 (※3) |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者1 (※4) |
8,000円 |
15,000円 |
※3 低所得者2とは、国保被保険者全員(擬制世帯主も含む)が住民税非課税の世帯に属する70歳以上の人を指します。
※4 低所得者1とは、国保被保険者全員(擬制世帯主も含む)が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する70歳以上の人を指します。
※5 過去12か月間に、1つの世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額になります。
※6 年間上限額は、8月診療分から翌年7月診療分の合計額をいいます。
限度額適用認定証
入院する時や、高額の外来診療を受けるときには、あらかじめ保険年金課の窓口で限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請してください。
この認定証を医療機関等の窓口に提出することにより、窓口でのお支払いが自身の自己負担限度額までとなります。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認できるもの
- 対象者の被保険者証
※所得区分が「一般」または「現役並み所得者3」の人は、限度額適用認定証が発行されません。
お手持ちの被保険者証と高齢受給者証を提示することで、自身の自己負担限度額の適用が受けられます。
※入院する医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、食事代の減額を受けられます。詳しくは当ページ「入院時の食事代」の項目をご覧ください。
限度額適用認定証申請書 (PDFファイル: 101.7KB)
限度額適用認定証申請書(記入例) (PDFファイル: 240.4KB)
高額療養費の支給申請
自己負担限度額を超えて医療費を支払った世帯には、診療月の3か月後以降に高額療養費の支給申請書をお送りします。
申請書が送られてくるまでお手続きいただく必要はありませんが、医療費の領収書は保管しておいてください。
※毎回の申請を省略する「自動払戻」の申請もできますので、希望される方はお問い合わせください。
※すでに申請書を受け取っている場合で、申請者が死亡しているときは、相続人が申請することができます。
お手持ちの申請書・下記「相続人用高額療養費支給申請書」・相続人の本人確認書類のコピーを送付してください。
相続人用高額療養費支給申請書 (PDFファイル: 322.2KB)
入院時の食事代
入院したときの食事代については、定額の自己負担(標準負担額)が必要です。
住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、標準負担額の減額を受けることができます。
※限度額適用・標準負担額減額認定証の交付については、当ページ「限度額適用認定証」の項目をご覧ください。
|
食事代の負担額 |
|
|
所得区分 |
1食あたりの標準負担額 |
|
一般(下記以外の人) |
460円 一部260円の場合があります(※1) |
|
住民税非課税世帯 |
210円(過去12か月間で90日を超える入院をしている場合は 160円) |
|
療養病床に入院したときの食費・居住費 |
||
|
所得区分 |
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|
一般(下記以外の人) |
460円 (※2) |
370円 |
|
住民税非課税世帯 |
210円 |
|
70歳以上の人
|
食事代の負担額 |
|
|
所得区分 |
1食あたりの標準負担額 |
|
一般(下記以外の人) 現役並み所得者 |
460円 一部260円の場合があります(※1) |
|
低所得者2 |
210円(過去12か月間で90日を超える 入院をしている場合は 160円) |
|
低所得者1 |
100円 |
|
療養病床に入院したときの食費・居住費 |
||
|
所得区分 |
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|
一般(下記以外の人) 現役並所得者 |
460円 (※2) |
370円 |
|
低所得者2 |
210円 |
|
|
低所得者1 |
140円 |
|
令和6年6月1日~
|
食事代の負担額 |
|
|
所得区分 |
1食あたりの標準負担額 |
|
一般(下記以外の 人) |
490円 一部280円の場合があります(※1) |
|
住民税非課税世帯 |
230円(過去12か月間で90日を超える 入院をしている場合は 180円) |
|
療養病床に入院したときの食費・居住費 |
||
|
所得区分 |
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|
一般(下記以外の人) 現役並所得者 |
490円 (※2) |
370円 |
|
住民税非課税世帯 |
230円 |
|
70歳以上の人
|
食事代の負担額 |
|
|
所得区分 |
1食あたりの標準負担額 |
|
一般(下記以外の人) 現役並み所得者 |
490円 一部280円の場合があります(※1) |
|
低所得者2 |
230円(過去12か月間で90日を超える 入院をしている場合は 180円) |
|
低所得者1 |
110円 |
|
療養病床に入院したときの食費・居住費 |
||
|
所得区分 |
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|
一般(下記以外の人) 現役並所得者 |
490円 (※2) |
370円 |
|
低所得者2 |
230円 |
|
|
低所得者1 |
140円 |
|
(※1) 小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者。
(※2)管理栄養士または栄養士により、栄養管理が行われているなどの場合です。
それ以外の場合は450円になります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




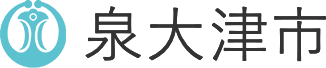

更新日:2024年06月10日