地域包括ケア会議
地域包括ケア会議とは
高齢者が住み慣れた地域で、できる限り自分らしい生活を継続していくことができるよう、個々の高齢者の状況に応じて適切な社会資源の活用やサービスの調整等を図っていくこと、また、それを支える保健・福祉・医療の専門職相互の連携、地域の様々な資源の統合などの整備を図っていくことを目的とした会議です。
泉大津市の地域包括ケア会議の構成
本市の地域ケア会議は、主に地域課題の解決に必要な地域づくりについて検討する 「構築会議」と、さまざまな個別課題などについて検討を行う「個別ケア会議」(権利擁護部会、自立支援部会、認知症部会)会議から構成されています。
包括ケア会議の内容
構築会議
|
内容 |
地域の課題を把握する。地域課題の解決に必要な地域づくりや資源開発について検討し、課題解決に必要な政策形成に繋げる。 |
|
参加者 |
保健医療関係者、司法書士等の専門資格者、介護支援専門員連絡協議会の委員、いきいきネット相談支援センター職員、社会福祉協議会職員、地域包括支援センター職員、関係行政機関職員等 |
| 開催日 | 年1回(3月の第4金曜日) |
|
議事内容(令和6年度) |
構築会議では、各部会(権利擁護部会、自立支援部会、認知症部会)の年間の取組について報告があり、その中で抽出された課題等について各専門職や行政で意見交換を行い、今後の政策形成について検討した。 |
個別ケア会議
1.権利擁護部会
| 高齢者の権利擁護の促進を目的に、多職種が専門領域の視点から個別事例について検討する。 施設への入所あるいは成年後見制度の市長申立等の対応が必要と判断される個別事例について市へ提言を行う。 |
|
|
参加者 |
保健医療関係者、司法書士等の専門資格者、介護支援専門員連絡協議会の委員、社会福祉協議会職員、地域包括支援センター職員、関係行政機関職員等 |
|
開催日 |
年4回(6月、9月、12月、3月の第2金曜日) 追加検討事例があった場合は随時開催 |
|
議事内容 (令和6年度) |
・親族の助けが得られず、認知症等内容であるため、生活に困っている方に対してどのような支援が適切かを支援者に助言。 ・高齢者虐待に関する事例における成年後見申立の必要性を審議。 |
2.自立支援部会
|
内容 |
高齢者の自立支援・介護予防に資するケアマネジメントの支援を目的に、多職種が専門領域の視点から個別事例について検討する。事例対象は、総合事業対象者、要支援者。 |
|
参加者 |
保健医療関係者、社会福祉協議会職員、地域包括支援センター職員、関係行政機関職員 |
|
開催日 |
毎月1回(年12回) |
|
議事内容(令和6年度) |
・膝関節痛と腰部痛があって日常の活動量の低下や外出頻度の減少しているケース ・運動能力が低下し、日常生活動作に困難さが生じ始めているケース |
3.認知症部会
| 内容 | 認知症高齢者等に対する個別課題解決のための検討及び支援に関すること、認知症高齢者等の介護等に関することについて検討する。 |
| 参加者 | 保健医療関係者、社会福祉協議会職員、地域包括支援センター職員、関係行政機関職員 |
| 開催日 | 年2回(6月、12月の第3金曜日) |
| 議事内容(令和6年度) |
・認知症の行動・心理症状等(BPSD)により、医療に繋がっていても家族だけで抱えきれないケース ・ACP(人生会議)、金銭管理と入院の備えについて |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




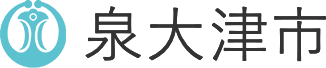

更新日:2025年04月01日