居宅サービスについて
居宅サービスを利用するには、まず介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。(自分で介護サービス計画を作成することもできます。)
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、サービス利用者などからの介護サービスの相談に応じ、適切なサービスが利用できるように介護サービス計画を作成し、介護サービス事業者と連絡・調整を行う者です。
※介護サービス計画の作成を介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼しても利用者負担はありません。
要介護1から5と認定された方には、次の居宅サービスがあります。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、食事、入浴、排泄などの身体介護や炊事、掃除、洗濯といった生活援助を行うサービスです。
訪問看護
訪問看護ステーション等の看護師や保健師などが家庭を訪問して、かかりつけの医師と連絡をとりながら、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行うサービスです。
訪問入浴介護
入浴が困難な寝たきりの高齢者などの家庭を入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問して、入浴の介助を行うサービスです。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等などが家庭を訪問して、療養上の管理及び指導を行うサービスです。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、入浴、食事の提供やレクリエーションや機能訓練を受けるサービスです。
通所リハビリテーション(デイケアサービス)
介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、その心身機能の維持回復と日常生活の自立支援のために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを受けるサービスです。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間宿泊して、食事、入浴、排泄などの日常生活上の世話を受けるサービスです。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、並びに日常生活上の世話を受けるサービスです。
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与するサービスです。
対象となるのは次の12種類です。
1.車いす
2.車いす付属品
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品
5.床ずれ防止用具
6.体位変換器
7.手すり(取付工事不要のもの)
8.スロープ(取付工事不要のもの)
9.歩行器
10.歩行補助つえ
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
※要介護1の方は、車椅子(付属品を含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として対象になりません。
特定福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合に費用の7~9割を支給するサービスです。 ( ただし、支給限度額は要介護度にかかわらず年間10万円です。また、都道府県の指定を受けていない事業所から購入された場合は支給は受けられません。)
対象となるのは次の9種類です。
※令和6年4月から、7~9の福祉用具について、貸与と販売の選択制が導入されました。
1.腰掛便座
2.特殊尿器
3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いすなど)
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具
6.排泄予測支援機器
7.スロープ
8.歩行器(歩行車を除く)
9.歩行補助つえ
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消など小規模な改修の費用の7~9割を支給します。
(ただし、支給限度額は要介護にかかわらず20万円です。また、改修工事施工前に事前申請が必要です。)
対象となるのは次の6種類です。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




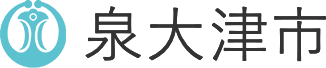

更新日:2024年04月01日