軽度者の福祉用具貸与の取扱いについて
次の福祉用具の貸与については、軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は、その状態像から使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象となりません。
・車いすおよび車いす付属品
・特殊寝台および特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具および体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト
・自動排泄処理装置※
※自動排泄処理装置については、上記の介護度の方に加え、要介護2・3の方も原則として保険給付の対象となりません。
ただし、利用者が様々な疾患等により貸与の必要性が認められる一定の状態にある場合や、医師の医学的所見とサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより貸与が必要であると判断される場合は、保険給付が認められます。
これらの場合の取扱いや必要な手続きについては、次の(1)または(2)をご確認ください。
(1)認定調査結果から、貸与の妥当性が認められる場合
要介護認定の認定調査結果から、別表1のとおり厚生労働省が種目ごとに示す一定の状態にある人については、福祉用具の貸与が認められます。
別表1に該当する場合は、申請書等は不要です。
(2)医師の所見とケアマネジメントから、貸与の必要性が認められる場合
上記の(1)に該当しない場合でも、別表2のとおり例外的貸与基準に該当することが医師の医学的所見に基づいて判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより貸与が特に必要と判断される場合は保険給付の対象となります。
この場合は、以下の書類を市役所高齢介護課に提出してください。
〇軽度者に対する福祉用具貸与のための理由書
〇利用者や家族の同意が得られているケアプラン(第1表から第3表又はA表からE表)の写し
〇サービス担当者会議の要点(会議録)
〇医療と介護の連携シート※
※医療と介護の連携シートを使用しない場合は、例外的貸与基準の該当性を医師に確認した方法と日時を記載した支援経過等を提出してください。また、医師の所見については、本人や家族から間接的に聴き取らず、必ず医師に直接確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




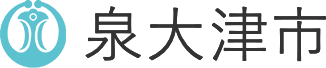

更新日:2023年08月01日