いずみおおつライブラリー 古の名残り
紀州侯のご休憩所 田中本陣(助松町)
突然、参勤交代のお殿さまの行列が現れても不思議でないような…紀伊徳川家小休所として本陣を承ってきた田中家は紀州街道沿いに当時のままの静かなたたずまいを見せ、「街道のまち」の面影を伝えています。
屋敷の広さは一町(約110m)四方。何度か改修されているものの、江戸時代前期の様式をよく残しています。また庭は石州流茶人として名高い藤林宗源の作で、宗源より贈られた片桐且元遺愛の石灯籠も端正な美しさをとどめています。田中家は清和源氏系統で新田氏とは同族と伝えられ、室町末期に郷士となり、江戸時代は大庄屋をつとめました。
(非公開・国登録文化財)

中世の栄華の面影をしのぶ泉穴師神社(豊中町)
石造りの太鼓橋のわきを通って足を踏み入れると、広い境内のむこうに二柱の神をまつる二つの鳥居。緑深い森には、ひときわ大きなクスノキが濃い影をおとす。
市内最大の神社、泉穴師神社は、江戸時代とほとんど変わらない景観で、訪れる人に安らぎを感じさせてくれます。
和泉五社のひとつとして仁明・清和など歴代の天皇による崇拝を受けてきた、由緒ある宮。中世には神宮寺であった穴師薬師寺とともに大いに栄えました。本殿のほか、摂社春日神社や住吉神社の本殿などが国の重要文化財に指定され、境内には楠木正成の奉納と伝えられる石灯籠も残されています。

弥生時代の暮らしの跡池上曽根遺跡(曽根町)

泉大津市曽根町と和泉市池上町にまたがる、約90万平方メートルの古代人の集落跡。たくさんの住居や、その周囲にめぐらされていた弥生代中期のものと推定される溝の跡、大量の土器・石器などが発見されています。当時としては有数の大規模なムラだったとか。じっと見ていると、この同じ場所で、米を作り生活を営んでいた弥生人の姿がうかんでくるようです。
平成3年には「府立弥生文化博物館」も完成し、当時の歴史により親しめるになりました。
穴師薬師堂(我孫子)

宝亀年中(8世紀後半)に浜に漂着した薬師如来をまつったのが始まりとされ、中世には穴師神社の神宮寺となり、七堂伽藍を備え、歴代天皇の崇敬もあつく全盛をきわめた。その後たびたび兵火にあい、現在では小堂の中に薬師如来像が安置されている。
寺町として現在の土台を築く南溟寺(神明町)

紀州街道よりさらに海よりにあった旧道付近には、17世紀後半の襖絵を残す南溟寺をはじめ、多くの寺院が見られます。この界隈は、かつて南溟寺を中心とする寺町であったらしく、最近発見された「大津村絵図」(1679年)には、そのころの様子がよく描かれています。
東西2町(1町は約110m)、南北3町の広さで、堀に囲まれ、旧道に直交する9本の道路が整然と並んでいて見事な都市計画ぶり。この中に、寺の僧侶と門徒の人々が住んでいて、職業からみると漁業と商業の町であったようです。海岸線と並行する普の2本の街道沿いは、現在も旧家が並び、落ち着いた雰囲気ですが、このあたりを中心に近代の泉大津のまちの土台がつくられていったのです。
曾根神社(曽根町)

創建は継体天皇のころとされているが定かでない。市内でいちばん古い由緒ある神社。本殿の建立は江戸時代末期から明治時代と思われる。境内には市の木「クスノキ」が茂り、閑静なたたずまい。
大津神社(若宮町)
明治41年、近辺の4社を合祀し、「若宮八幡神社」から現在の「大津神社」に改称した。江戸時代前期の石造物が多く、寛永元年(1624年)の銘のある2基の石灯篭や寛永20年銘の石鳥居などが、どっしりとした歴史の重みを感じさせる。

蟹塚(河原町)

元禄時代に宇多大津村の庄屋、横山氏が新田を開発した際、作物を荒らすカニを多数撲滅した。後にその菩提を弔うため、「蟹塚」を建立したと伝えられる。
助松神社(助松町)

8世紀なかごろ創建されたといわれ、13世紀前半には菅原道真公が合祀されたことも。本殿は柱と柱の間が偶数になるよう造られためずらしい設計。境内には17世紀後半の鳥居や手洗鉢、百度石も見られる。
四十九山(千原町)

戦国時代の豪族で、千原城主、玉井壱岐守源秀の墓所。細川氏綱の家来として戦いに参加し、天正16年(1588年)5月に没した。いまでは当時をしのばせるものは少なく、わずかに墓碑だけが面影をとどめている。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




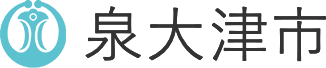

更新日:2023年11月13日