中学校の授業で認知症サポーター養成講座を開催(平成27年2月24日)
まちぐるみでの認知症サポートに向けた新たな試み!
次代を担う誠風中学校2年生約320人が認知症サポーターに加入
認知症サポーター養成講座が23日、泉大津市立誠風中学校(泉大津市池浦町4-1-1 校長:浦西典昭)の2年生を対象に実施され、生徒約320人と学年担当教員が参加した。中学校の授業で同講座を開催するのは同市では初の試み。
同講座は「認知症を知り地域をつくるキャンペーン」の一環として市職員・介護事業所職員・医療関係者などが講師となり開催されている。「認知症サポーターキャラバン事業」は全国で展開されており、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者としてその役割が期待されている。
今回の狙いはずばり次世代育成。2025年、日本は超高齢化社会を迎える。同市ではその時の担い手として若い世代の育成に力をおいており、今年度は小学校(約110人)やだんじりの青年団(約200人)向けの講座も開催。これまでに約2,250人の認知症サポーターが誕生している。
誠風中学校では認知症サポーター養成講座を、総合的な学習のなかで地域の役に立てる生徒を育成する福祉学習の一環として開催。2年生では「高齢者理解に関する学習」をテーマに、体の動きにくさを体験する疑似体験などを経験したのち、高齢者に多い認知症に対する理解を深めようと講座が実施された。
当日は、講義「認知症とは?」に始まり、認知症になったお爺さんと暮らす家族の日常を描いた寸劇、具体的にどのように認知症の人と接するとよいのかをDVDで観るなどの60分。なかでも寸劇では、何度も入れ歯の場所を聞くお爺さんの様子に戸惑いと笑いが起きるとともに、お爺さん自身が気持ちを語る場面になると生徒たちは真剣な表情で聴き入っていた。講師から「毎日何回も同じことを聞いてきたらどうしますか?」との質問に、会場の生徒からは「ちゃんといっぱい話を聞いてあげる」「その人といっぱい会話をする」「言ったことを紙に書いてあげる」といった意見が出された。
最後に講師から、サポーターとしてこれからできることとして、「まずは理解者になること」「偏見を持たずに接すること」「今日受けた講座のことを家で話してみること」と語りかけられ、生徒からは「認知症がわかった」といった声があがり、この日サポーターに加わった生徒たちはその証であるオレンジリングを手に誇らしげな笑顔を見せていた。
浦西校長は「子どもたちが認知症を理解し、優しくあたたかい気持ちを持って接するきっかけになってくれたと思います」と話していた。

この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




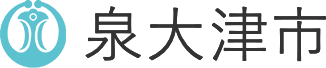

更新日:2023年08月01日