12月20日から、家族でコロナ時代の災害に備える取り組みを開始!
特典は吉野家の1000食限定“炊き出し支援牛丼”
【家族でコロナ時代の災害に備える】
阪神淡路大震災から27年。親世代も震災経験がない家庭が増えています。一方、コロナ禍の今、これまでの経験が通用しない場合もあります。
そこで、市では12月20日(月曜日)から来年1月17日(月曜日)までの1か月間、“コロナ時代”に家族で防災について「考え、行動」するための取組みをスタートしました。
【家族で“考える”。特典は“炊き出し支援牛丼1000食”】
市の啓発だけではなかなか興味を持っていただけません。そこで牛丼の吉野家や地元FM局の「FMいずみおおつ」とのコラボで、家庭での備蓄や災害放送をラジオで聞く習慣を身に付ける活動に取組みます。
取組みは「ネットコース」と「はがきコース」の2種類。いずれかに取り組んだ方限定1000名に、吉野家の“炊き出し支援牛丼”を1月16日(日曜日)に開催する防災イベントで提供します。
「ネットコース」は、自宅にある食料などでローリングストックできるものを探し、写真を撮り、ネットで申し込み、「はがきコース」は、FMいずみおおつで放送される「おづみんタイム」で出題されるキーワードを聞き、はがきで申し込んでいただきます。
【家族で“行動する”。震災疑似体験イベントを開催】
1月16日(日曜日)午前10時から避難所協定を結んでいる住友ゴム工業株式会社泉大津工場(河原町9-1)で震災を疑似体験できるイベントを開催します。
イベントでは事前に申し込みをしている1000名の方に牛丼をお持ち帰りいただきます。しかし、目的は“物”ではなく、“物語”を持って帰っていただくこと。そこで、各ブースに持って帰っていただきたいストーリーを込めています。
【東日本大震災から。“吉野家”“防災無線”の物語】
吉野家はキッチンカー1台で1000食の炊き出し牛丼を提供。東日本大震災の支援活動をリアルに再現します。
また、東日本大震災では約6割の住民が防災無線の放送を聞くことができませんでした。緊急情報の聞きのがしをなくすため、来月1月から導入する「放送内容がスマホに音声と文字で届く」アプリの紹介などもします。
【コロナ禍での気づき。“避難所テント”“WOSH”“ジェンダー”】
一方、コロナはこれまでの災害対策を見直すきっかけにもなりました。コロナ時代の新しい気づきや変化も踏まえ、感染症対策とプライバシーに配慮した避難所用テントを設置。避難スペースの広さやベッドの寝心地を体験いただきます。
また、12月に整備した水道がなくても使える水循環型手洗いスタンド“WOSH”も展示。WOSHは正しい手洗いに必要な“30秒をカウントする機能”や“スマホ除菌の機能”も搭載。新しい衛生対策も体験いただきます。
災害対策を見直す中で、過去の震災課題でジェンダーギャップの問題が見過ごされてきたことに改めて気づきました。「コロナ×災害×ジェンダー」をメインテーマとした展示ブースも設置します。
【新しいボランティアのかたち。“高校生デジタルボランティア”】
コロナ禍では急速にデジタル化が進展しました。デジタル化社会で高齢者が取り残されないよう、地元高校生が疑似避難所のデジタルボランティアに。高校生がアプリの使い方などをサポートし、デジタルと災害への不安を取り除きます。
【家族で防災について話しあう。“家族防災会議の日”】
平成29年に実施した市民アンケートでは、約6割の市民が「家庭で防災対策をしていない」と回答しています。そこで家族で防災について話しあうきっかけをつくるため、1月17日を市独自の記念日「家族防災会議の日」としました。今回のイベントで得た経験なども踏まえ、家族で防災について話しあっていただきたいと考えています。




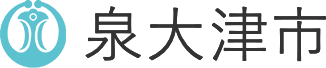

更新日:2023年08月01日