泉大津市指定文化財の新規指定について(令和3年1月20日)
市指定有形文化財の指定について、田中家文書が、令和3年12月16日に泉大津市文化財保護審議会(会長 吉原忠雄 元大阪大谷大学教授)から市教育委員会へ建議されました。市指定文化財として、令和4年1月20日に告示されますので情報提供いたします。
今回新たに指定される田中家文書は、泉大津市助松町に所在する田中家に代々伝わる文書です。江戸時代に紀州徳川家御用の御休本陣として参勤交代などの際に使用され、助松本陣と呼ばれてきました。本陣としての役割を持つ以外にも、地域の大庄屋も勤めていたことから、本市の近世・近代の様相を知るための貴重な文化財です。
名称及び年代
田中家文書 近世~近代 文禄4~昭和5年(1595-1930)
種別 有形文化財(古文書)
数量 34,804点
【概要】
本文書は、助松村はもちろんのこと、泉大津市域や泉州地域においても屈指の有力者であった田中家の江戸~明治時代を中心とする史料群である。
その内容は、政治・経済・社会・文化の幅広い分野にわたり、田中家の1.豪農・名望家として家業や生活を営む私的な面と、2.庄屋や戸長として行政・自治を担う公的な側面とをバランスよく含んでいる。公私にわたる豊かな史料が、それらを収める建造物と一括で、良好な状態で保存されてきた点からも、本文書の歴史的価値は高い。
質・量ともに優れた近世・近代の史料群であり、泉大津市域や泉州地域はもちろんのこと、大阪府域や近畿地方の歴史と文化を考えるうえでも貴重かつ有用なものである。
【文化財の所有者】 泉大津市
【田中家文書 詳細解説】
本文書は、泉大津市内の助松に代々居住し、江戸~明治時代に庄屋や戸長をつとめた田中家に伝えられた史料群である。当主の田中愛昭氏より泉大津市に寄贈され、現在は織編館で保管されている。
本文書に収録される史料は、全体で34,804点が確認されている。このうち作成年の判明する8,150点余をみると、文禄4~昭和5年(1595-1930)という330年余の期間にわたるが、その中心は、延宝期(1673-81)から明治期(1868-1912)にかけての文書・記録類である。収録する数量や期間に恵まれた本文書は、市内随一の近世・近代史料群であることから、『泉大津市史』(本文編・史料編)の編纂に際しては、江戸~明治時代に関する最重要の素材として多数用いられている。
江戸時代の助松村は、現市域の北西部に位置し、紀州街道に沿って集落を形成し、西側は大阪湾に面した。米・麦や木綿・菜種の生産が盛んであり、漁業も行われた。領主・所領については、豊臣家の滅亡後に幕府領となる。宝暦13~寛政7年(1763-95)と文政7~安政2年(1824-55)に御三卿の清水家領となったが、それ以外の時期は幕府領である。村高は、慶長2年(1597)に671石余、延宝5年(1677)880石余、天保5年(1834) 887石余、明治元年(1868)ごろ885石余。戸数・人口は、宝永7年(1710)に146戸・ 682人、寛政4年(1792)143戸・580人(本村分90戸・356人と枝村の蓮正寺分53戸・224人)、文久元年(1861)177戸・863人(本村分114戸・539人と蓮正寺分63戸・324人)。
明治時代の助松村は、同4年に堺県の管轄となり、翌5年に和泉国第12区、7年に和泉国第2大区4小区4番組、13年に大鳥・泉郡役所内第5連合に属した。翌14年に堺県が廃止されて大阪府に編入されると、助松村は一村で戸長を置き、17年には第27戸長役場に属した。しかし22年、第27戸長役場に属する8か村が合併して上条村が成立すると、助松村は大字助松となった。昭和6年(1931)に上条村が大津町や穴師村と合併して大津町となり、同17年さらなる合併で泉大津市が成立した際にも、助松は大字として存続し、43年に市内の町名となった。村の戸数・人口は、明治7年に182戸・ 890人、同18年182戸・1,040人。
本文書を所蔵していた田中家は、清和源氏の新田氏につらなる一族で、元亀期(1570-73)に重景が来住したという。また、重景は遠江守を称して織田信長の手に属し、天正5年(1577)に石山(大坂)本願寺攻めで戦死して、田中家累代の墓所となる牛滝塚に埋葬されたと伝える。その子孫は代々助松に居住した。江戸時代には、当主が覚右衛門(または角右衛門)を名乗り、多くの田畑をもつ豪農であるとともに、助松村の庄屋をつとめた。田中家の持ち高は、明和3年(1766)150石余、文化3年(1806)123石余など、村内で最も多い100~150石台を保ったが、同13年の86石余以降、相続による分地などで次第に減少した。また、田中家は二枚池や新池など村内の溜池を築造したと伝えられ、その管理権を有した。さらに、同家の住宅は、紀州街道に面して広大な敷地と数々の建物を有するが、紀州藩主が参勤交代する際の小休所となったことから、助松本陣(あるいは田中本陣)とも呼ばれる。
明治時代には、田中家当主の多井二郎が同3年(1870)に助松村の庄屋、5年に第12区助松村の戸長、7年に第2大区4小区4番組5カ村の戸長、13年に第5連合28カ村の戸長、15年に助松村の戸長、17年に第27戸長役場8カ村の戸長を歴任した。つづく楠三郎も、11年に助松村の惣代、17年に大鳥・泉両郡連合会の議員、22年に上条村の議員をつとめるなど、地域の行政や自治を担った。ただし、明治30年代以降、田中家の活動は、行政や政治から離れ、地主経営や医業などが中心となる。
本文書は、助松村はもちろんのこと、泉大津市域や泉州地域においても屈指の有力者であった田中家の江戸~明治時代を中心とする史料群である。その内容は、政治・経済・社会・文化の幅広い分野にわたり、田中家の1.豪農・名望家として家業や生活を営む私的な面と、2.庄屋や戸長として行政・自治を担う公的な側面とをバランスよく含んでいる。主な内容をあげると、次の通りである。
(1)江戸時代
- 支配・村況 奉行所や領主・代官からの法令と村からの訴願や届、年貢の賦課・納入や廻米といった支配に関する史料、村(本村分と枝村蓮正寺分)における戸数・人口や田畑の面積・石高の調査など村況の史料。
- 村政 所領の村々や一村内の協定、村の役職をめぐる訴訟、溜池の水利をめぐる隣村との紛争など村政の史料。
- 産業・交通 漁業者の人数や漁船・漁獲高の調査など漁業の史料、木綿・菜種の栽培や売却・運送、紀州藩領における売薬といった農業や商工業に関する史料、宿駅の助郷や廻船、紀州藩主の参勤交代など交通に関する史料。
- 宗教・生活 由緒・本末の調査や檀家との紛争など寺社に関する史料、農業の重要事項や当時の世相、伊勢参りや熊野詣など生活文化に関する史料。
- 書状 田中家の家族・親類や友人・知人、領主・代官の役人や地域住民、取引先などとの間で交わされた書状類。
(2)明治時代
- 行政・村況 大区小区戸長役場の廃止と連合戸長役場の設置、戸長・議員の選挙や村会の規則など行政に関する史料、住民や役人による土地の調査と新租の設定、新地券の発行といった地租改正の史料、消防の人員・備品や巡査の配置のような警察・消防に関する史料、村の絵図や石高・面積・戸数・人口・社寺・学校・物産の調査など村況の史料。
- 産業 漁業者の人数や漁船・漁獲高の調査など漁業の史料、村ごとの物産の種類や米・麦・綿の作付面積・収穫高・旱損の調査のような農業に関する史料、村における物価・職工賃銀・営業人数の調査など商工業の史料。
- 通信・交通 郵便線路の設定や電信・電話線の敷設といった通信に関する史料、紀州街道の修繕や大津川の架橋、南海鉄道の敷設など交通に関する史料。
- 軍事 信太山射場での演習、浜寺俘虜収容所の病室建設など軍事の史料。
- 教育・宗教 堺県による小学区分の改正、村における学齢人員の調査と学資金の賦課、助松小学の校舎建築や尋常小学校の設置のような教育に関する史料、村の社寺調査と廃寺、神社の建替や祭礼など宗教の史料。
- 手紙 田中家の家族・親類や友人・知人、府県・郡村の役人や地域住民、取引先などとの間で交わされた書状類。
なお、本文書を伝えてきた田中家の住宅には、江戸時代以来の伝統的な建造物が多く残され、平成19年(2007)、主屋・備窮倉・築地塀・玄関及び座敷棟・表門・勝手門及び納屋の6件が国の有形文化財(建造物)に登録された。公私にわたる豊かな史料が、それらを収める建造物と一括で保存されてきた点からも、本文書の歴史的価値は高い。
以上のとおり、本文書は、市内の助松に代々居住し、江戸~明治時代に庄屋や戸長として行政・自治を担うとともに、豪農や名望家として地域の経済・社会・文化に大きな役割を果たした田中家の公私にわたる2万点余の文書・記録類をまとまった形で伝えている。質・量ともに優れた近世・近代の史料群であり、泉大津市域や泉州地域はもちろんのこと、大阪府域や近畿地方の歴史と文化を考えるうえでも貴重かつ有用なものである。
《参考文献》
『和泉国助松村庄屋日記』
『泉大津市の地名』〈泉大津市史紀要第1・8号〉
(泉大津市史編纂室編、泉大津市教育委員会、1977・84年)
『泉大津市史 第1巻下 本文編2』
『同 第2巻 史料編1』
『同 第3巻 史料編2』
『同 第4巻 史料編3』『同 第5巻 別編・史料編補遺』
(泉大津市史編さん委員会編、泉大津市、1983・86・88・95・98年)
『田中家文書目録:泉大津市助松町(助松本陣)1(近世編)』
『同2(近代編)』『同3』〈泉大津市史料室紀要1・3・5〉
(泉大津市教育委員会・泉大津市史料室、2010・11・12年)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-33-0670




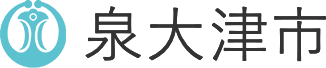

更新日:2023年08月01日