「SOSの出し方に関する教育」を実施(令和5年5月2日)
~自殺予防対策~
市内すべての中学1年生を対象に「SOSの出し方に関する教育」を実施
厚生労働省の発表では、昨年、自ら命を絶った児童生徒は514人と統計開始以降最多となり、国では、小中高生の自殺者が増えていることを重く受け止め、昨年10月に閣議決定された新たな自殺総合対策大綱では、特に子ども・若者への自殺対策のさらなる推進強化の一環として「SOSの出し方に関する教育」の推進を位置付けています。
「SOSの出し方に関する教育」とは、命や暮らしの危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればいいのか具体的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、つらいときや苦しいときは助けを求めていいことを学ぶ教育です。
泉大津市では、今年5月に授業の一環として市内の中学1年生を対象に、自殺対策の専門家を講師に迎え「SOSの出し方に関する教育」を実施します。授業内容は、講師からの講話「大切な自分、かけがえのない友だち」を聴いた後、生徒が二人一組となり聴き手と話し手に分かれ、話し手は心配事や悩みなどの聞いてほしいことを話し、聴き手は「うなずき」「あいづち」を打ちながら、否定しないで話の内容をそのまま受け取るなど、友だちが悩んでいることに気づいたときに、悩みを上手く聴きだせる方法をロールプレイング形式で演習します。
市では、特に増加傾向にある若年層や女性の自殺リスク低下をめざし、9月の自殺予防週間にLINEによる相談窓口を開設し、幅広い年代層と特に若年層や女性の悩みや不安を気軽に相談できる体制を整備します。また、自殺予防を含めた孤独・孤立対策の一環として、悩みに応じた相談先や支援制度などをまとめた「泉大津市孤独・孤立対策ポータルサイト」を昨年12月に開設。同サイトは、市ホームページからアクセスが可能で、木々の緑をイメージしたトップページは、親しみやすさと安心感を与えるデザインとし、悩みごとの内容やライフステージなど属性を示した入口を数パターン配置し、課題解決に向けたページにたどり着きやすく工夫しています。掲載内容は、市の支援情報を横断的に網羅し、国・府などの情報も数多く掲載し、継続的・一元的な情報管理とタイムリーな情報発信が可能となっています。
なお、ポータルサイトの開設と同時に悩みに応じた相談窓口・居場所・支援制度などをまとめた冊子を作成し、市内全世帯へ個別配布を行いました。
さまざまな取り組みを行ってきた市では、令和2年に17人とピークとなった自殺者数は、年々減少し令和4年では9人となっています。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




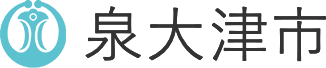

更新日:2023年08月01日