おうちで体験学習 ものの模様を写してみよう!
おうちで楽しく歴史の勉強をしてみましょう!
今回は、ものの模様を写す、拓本(たくほん)を紹介します。
拓本とは?
拓本は、石碑などに刻まれている文字や模様に直接、紙を当てて墨などで凹凸を写し取る技法です。これは、模様の凸部に墨がつき黒くなり、凹部が白く残ることで紙に模様が写ります。
簡単なものでは、紙の下にコインなどを置いて、それをえんぴつでこすることでものの輪郭を写しとる方法があります。
今回はそれを実際に体験してみましょう!
拓本の方法
1.必要な道具
以下の道具を用意します。
- えんぴつ
- 紙
- 模様を写したいもの(コインなど平たい物が写しやすいです)

2.紙の下にものを置く
模様を写したいものを紙の下に置きます。

3.えんぴつでこする
えんぴつでこすり、ものの模様を写しとります。えんぴつを斜めに当てると写しやすいです。


4.完成
ものの模様が写しとれたら、名称と日付を書いて完成です!

拓本の種類
拓本には乾拓(かんたく)と湿拓(しったく)の二種類があります。乾拓は今回紹介した方法で、紙を湿らさずに墨などでこすり模様を写しとります。湿拓は紙を湿らせて写しとりたいものに貼りつけ、タンポという道具で墨を打ち込み模様を写しとります。考古学では、ものに直接貼りつけて写しとることができる湿拓の方が多く使われており、乾拓は水気を嫌う刀剣や木製品などで使われます。
似た方法に魚拓(ぎょたく)がありますが、これはものに直接、墨をつけて紙に写しとるため、文化財を汚してしまいます。そのため、考古学で使われることはありません。

湿拓の道具
(下から三番目までの道具がタンポ)

湿拓の実例
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




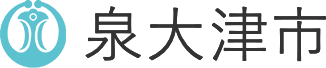

更新日:2023年08月01日