おうちで体験学習 紙コップで銅鐸をつくってみよう!
紙コップであなただけのオリジナル銅鐸をつくってみませんか?
銅鐸とは弥生時代におまつりに使用されていたと考えられているものです。
関西にある遺跡から多く出土し、大小さまざまな大きさのものが見つかっています。
いろいろな模様がかかれており、中には動物や人物がかかれているものもあります。
紙コップの銅鐸、ちぢめて紙鐸。みんなでつくってみましょう!

紙鐸のつくりかた
1.用意するもの
- 紙コップ 1つ
- はさみ
- のり
- えんぴつ
- 色えんぴつなどの色をぬるためのもの
- 下記のPDF(印刷用)を印刷したもの(印刷できない場合は紙1枚)

紙鐸きりとり用紙(A4用) (PDFファイル: 56.9KB)
2.絵をかいたり色をぬる
まずは印刷した用紙の枠内に絵をかいたり色をぬったりしましょう。
昔の人もいろいろなもようをかいていました。
下記のサイトなども参考にしてください。

3.はさみで切る
きりとり用用紙にある鐸身(たくしん)や鈕(ちゅう)を形に合わせてはさみできりましょう。

きれたら、鈕(ちゅう)のキリヌキ部分をきりとります。
まず、鈕(ちゅう)の部分を横に半分に折ります。

折れたらきりとる部分をはさみできりとります。

4.折る
折れ目にそって鈕を折りましょう。
折るときはやまおりにしましょう。

5.貼る
まずは紙コップの側面に紙をはります。
のりしろとかかれた部分にのりをつけ、紙コップに紙をまきつけてはりつけましょう。
のりしろにものりをつけ、紙コップの底面にはりつけましょう。
(鈕の内側上部をのりではりつけるとよりきれいな形になります)


鈕(ちゅう)がひらいているのが気になる人へ
鈕(ちゅう)が開いていて気になる人は鈕(ちゅう)の上部の内側にのりをつけて両面をはりつけるときれいに仕上がります。


6.完成!
これで完成です!
鉛筆で紙コップを叩くと音がなりますよ!
昔の人もこのように棒でたたいたりして音をならしていました。
実際の銅鐸は金属なので鐘(かね)のような音がなります。

- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




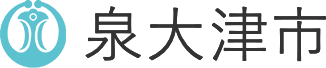

更新日:2023年08月01日