千原町(ちはらちょう)
千原村は、江戸期~明治の村名。明治22年合併、上条村の大字となる。昭和6年大津町の大字、昭和17年泉大津市の大字となる。明治8年戸数70戸、9年人口348人。
地内には、「千原城」の言い伝えがあり、水路が住宅を取り囲むようにながれ堀をほうふつさせる。城は、字「兵主原」と思われ、その地には「菅原神社(天満宮社)」があり、明治42年曽根神社に合祀されるが神社は拝殿として残され、その後、菅原道真が改めて祭られて地元の信仰をあつめている。
中世末の明応2(1492)年千原彦太郎なる武士がみえ、後に玉井氏を称すという。千原城の城主は、玉井壱岐守行家源秀で、その領地は千原村・森村という。行家は、両細川家の乱にあたり、細川氏綱の旗下に属し、侍大将として天文12(1543)年堺南荘に討ち入るも芦原口にて細川晴元方の松浦肥前守と戦い玉井勢三十余討死し退く、同年和泉横山合戦で三好孫四郎(長慶)と争いまた敗れる。後、永禄4(1561)年河内高屋城より千原に帰り、上条郷に270町歩を領する。天正16(1588)年没し「四十九山」に葬られる。
畦田池は、昭和44年埋め立てられ「条東小学校」が昭和45年9月完成、畦田公園が開設される。 「千原町一丁目、二丁目」は昭和48年2月1日住居表示実施により、尾井千原・森の一部を含め新設される。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




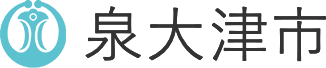

更新日:2023年08月01日