アビリティタウン構想とは
我が国の人口は長期にわたる減少局面に突入し、2053年(令和35年)には1億人を割り込むと予測されています。特に、生産年齢人口(15~64歳の人口)の減少、後期高齢者である75歳以上の人口の増加は、経済面では成長の制約要因となり、財政面においては医療・介護費の増加により財政運営にも大きな影響を与えることになります。
本市においても、2005年(平成17年)の77,673人をピークに減少傾向で推移しており、2019年(平成31年)には74,759人と、この間、14年で約3千人もの人口が減少しております。2005年(平成17年)には、年少人口が老年人口を下回るなど、日本社会が直面する課題は、「泉大津の課題」でもあります。
我が国は、高度経済成長を経て、様々な技術が進歩し、ものが溢れ、便利な時代となった一方で、目まぐるしい社会情勢の変化により、人々は「心」のバランスを失い、多くの負担を抱える「ストレス社会」であると言われています。
これからの日本社会においては、人々が心身共に健康で快適に生活することができるよう、自分の身体は自分で「整える」ことが重要であり、行政課題として捉える必要があると考えています。
そこで、本市では、身体及び認知機能や能力、技量、才能など広く健康を「アビリティ」と捉え、市民一人ひとりが「能力」、「技量」、「才能」を伸ばすとともに、泉大津市民としてまちへの愛着と誇りを持つシビックプライドの醸成を図り、都市ブランドとしての「アビリティタウン」の実現を目指しています。既に、市民活動の場や保育・教育の場では、身体機能を取り戻す「あしゆびプロジェクト」や人が本来持つ能力を最大限に引き出す「ビジョントレーニング」や「ブレインブースト読書教室」などのアビリティ関連事業を実践しています。
今後はさらに、健康増進のための選択肢を増やし市民の積極的な取り組みを促すことを目的に、アビリティ関連事業者の誘致及び活躍の機会、実証の場の創出、並びに大学・研究機関等の関係機関との連携を図り、様々な社会課題の解決モデルを生み出す仕組みとしての「リビングラボ」の構築を進めてまいります。
市民会館等跡地では、このアビリティタウン構想の実現に向けて、三つの目標を持って取り組みます。
一つ目は、かつて賑わいのあった泉大津駅西地区の活性化、臨海部との連携や賑わいの創出です。二つ目は、自分の身体を自分で「整える」ための核機能としてのアビリティ拠点を整備し、「リビングラボ」の中心的な役割を担うとともに、市内で展開される様々な事業・取り組みを束ねるプラットフォームを形成することで、まち全体の魅力向上と、市民一人ひとりのシビックプライドの醸成を実現することです。そして三つ目は、広大な市民会館等跡地空間と臨海部の緑地空間とを連動し、多様なアクティビティの創出、様々なことをトライアルできる空間の創出です。
市民会館等跡地では、現在、取り組んでいるアビリティ関連事業、南海本線高架下の活用、スポーツ施設等との連携、リビングラボの構築などと連動し、本市の「アビリティタウン」の実現に向けた一つの事業として展開して参ります。
我が国の共通課題を解決するモデル事業を公民連携市民共創で、この「泉大津」から発信します。

市民会館等跡地活用に係る民間事業展開に関する問合せ
本市では、アビリティ関連事業者との対話を随時募集しております。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




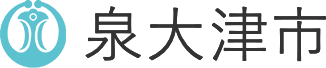

更新日:2023年12月11日